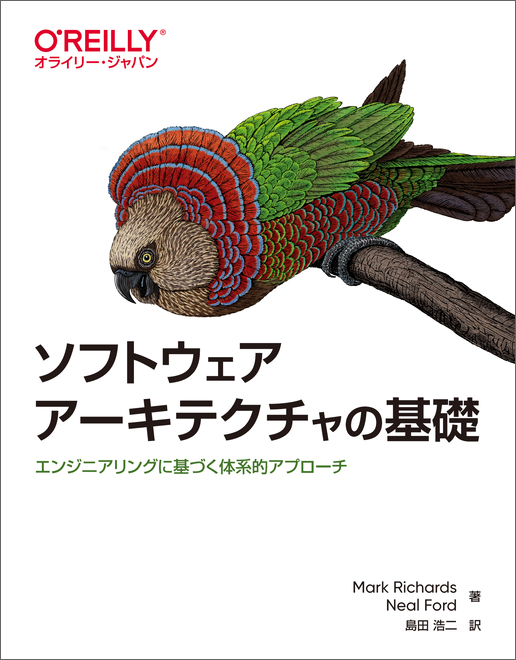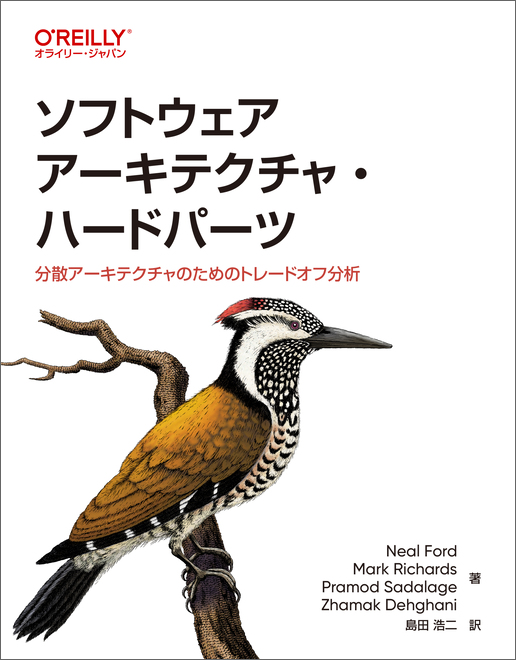目次
findy主催のアーキテクチャconference2024に参加したので、その感想を備忘録的に書き残したいと思います。
参加経緯
このイベント自体は社内でセミナーに積極参加している方が社内チャットで告知してくれていたのをきっかけに知りました。
最近設計タスクをやるようになったこともあり、もっとアーキテクチャの知見を深めたいと思っていたところだったのでフッ軽に申し込みました。
ただ、自分が申し込んだのはイベント1週間前で、懇親会の抽選期限は当然過ぎていましたし、満員で申し込めないセッションも結構ありました。
やはりセミナーは早めに申し込むのが吉ですね。
会場の雰囲気
やはりアーキテクチャという間口の広いテーマだからか、平日かつ初開催にも関わらず会場は人でごった返していました。
そして無料イベントなのに案内、司会、お弁当まで本当にしっかりしていてクオリティが高い!
findyさんのイベント企画・運営力半端ないです...

加えて至るところにアーキテクチャ図がおいてあって歩いてるだけでもめちゃくちゃ面白いし勉強になりました。
なにより、クラシルやMIXI、DMMのような誰もが知ってる企業のアーキテクチャやその選定理由が普通に掲載してあって「いつも使ってるあのアプリはこういう仕組みで動いているのか~」という感動がひとしおでした。

印象に残ったセッション
キーノート
「ソフトウェアアーキテクチャの基礎」や「ソフトウェアアーキテクチャ・ハードパーツ」の著者として知られるNeal Fordさんの基調講演でした。
自分はこの日のためにソフトウェアアーキテクチャの基礎を軽く読んでから挑んだのですが、それが功を奏してかなりの部分理解することができました。
また、ソフトウェアアーキテクチャの基礎を読んでからずっと気になっていた設計とアーキテクチャの違いについて時間をかけて説明してくれたので個人的には本のわからなかった部分を補完してくれている感じで大変有意義でした。
ソフトウェアアーキテクチャ・ハードパーツもスーパー名著と名高いのでソフトウェアアーキテクチャの基礎を読み終わったら読みたいな~と思っています。
3社と語るAWS Architectureレビュー会
ランチタイムセッションだったのでお弁当をいただきながら聞こうとしたのですが、これが罠!
あまりに濃い内容にすぐさま「弁当食ってる場合じゃねえ!」となりました。
3社ともワークフローのアーキテクチャを持ってきていて、step functionsを使ってフルマネージドにしたりSQSで非同期処理を行ったりと、正直自分には改善策がパッとわからないくらい素晴らしく作り込まれていました。
ですが、そこはさすがのAWSチーフテクノロジスト内海さんで言われればなるほどな~となるような改善策をしっかり用意してくださっていました。
なにより、ベストプラクティスはないけどセオリーはある、ということでセオリーをできるだけしっかり頭に入れておくことが良きアーキテクトへの第一歩なのかなと思ったりしていました。
140年の歴史あるエンタープライズ企業の内製化×マイクロサービス化への航海
まず杉山さんの話がめちゃくちゃおもしろかったです。
そして、内容自体も「企業としての歴史は長いのにソフトウェア開発の歴は短い」という一番しがらみに苦悩しそうな状況での葛藤を話してくださっていて、多くの日本の大企業で起こってそうな話だと思いながら聞いていました。
しかし、自分が一番驚いたのはそんな苦闘しそうな中でこれだけモダンなアーキテクチャをこの短期間で実現できたという部分です。
一体どう進めていったのか、という詳細を聞きたいな~と思わせられる素晴らしいセッションでした。
イオンCTOが語る イオングループ全体を支えるクリティカルシステム 解体新書
まず、山崎さんの話がめちゃくちゃ面白いです。(というか今回の登壇者全員話うますぎました)
内容的には「いろんな背景でバラバラだったグループのユーザーアプリを統合したい!」というビジョンのもとでリアーキテクチャをしたという話でした。
種々の背景でAzureを使わざるを得なかった話やキャッシュ戦略で可用性を向上させた話などそれぞれのトピックが非常に面白いセッションだったという印象です。
また、プロダクト世界観を持ったうえでそれに合わせてアーキテクチャを作っていくという視点は今の自分には持てていないものなのでとても学びになりました。
終わりに
今回のイベント、個人的にはかなり学びになりましたし、刺激にもなりました。
特に自分くらいの若手はアーキテクチャを考える機会は少ない、けど経験しないとできるようにならないというジレンマを抱えがちなので、今回のような機会はとても貴重です。
また、社内でアーキテクチャ検討会みたいな企画を作れないかな~と画策するきっかけにもなりました。
来年も日付決まっているので、次こそは早めに申し込んで懇親会の抽選をゲットしたいと思います。